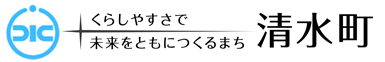2025年3月28日 更新
国民年金について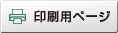
申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認でき、マイナポータルのアカウント設定でメール通知を希望している方には、マイナポータルに審査結果が届くとメールでお知らせします。
24時間どこからでも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
電子申請の方法は、日本年金機構HP(個人の方の電子申請(国民年金))をご覧ください。
国民年金制度について
国民年金の被保険者の種別は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
結婚や就職、転職、退職などで第1号被保険者に加入する場合は、2週間以内(第2号被保険者になった場合は、勤務先の事業主が手続きを行います。)に、下記窓口で手続きが必要です。
その場合、退職された日の翌日から国民年金に加入することになります。
| どんな人が? | 加入の届出は? | 保険料の納付は? | |
| 第1号 被保険者 |
・学生 ・自営業者 等 |
ご自身で清水町役場へ届出 | ご自身で納付 |
| 第2号 被保険者 |
・会社員 ・公務員 等 |
勤務先が届出 | 勤務先で納付 |
| 第3号 被保険者 |
第2号被保険者 の被扶養配偶者 |
配偶者の勤務先へ届出 | なし(配偶者が加入する 制度が負担) |
〔日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者です。〕
【任意加入制度】
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
また、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も加入することができます。
国民年金保険料の納付について
年金保険料は、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリまたはねんきんネットを活用した納付書によらない納付のいずれかの方法で納付が可能です。
また、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用される制度もあります。
詳細は、日本年金機構HP(国民年金保険料)をご覧ください。
2.保険料の追納について
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
このため、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
詳細は、日本年金機構HP(国民年金保険料の追納制度)をご覧ください。
3.付加保険料について
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
ただし、国民年金保険料の納付を免除されている方、国民年金基金の加入員である方は対象外となります。
詳細は、日本年金機構HP(付加保険料の納付)をご覧ください。
国民年金保険料免除等制度
1.保険料の免除・猶予について
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、前年所得等の審査により、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
沼津年金事務所、役場窓口または電子申請によりお手続きできます。
| (1)全額免除 |
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が全額免除になります。 <所得額の基準> (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| (2)一部納付申請 |
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が一部納付(一部免除)になります。 <所得額の基準> (4分の1納付の場合) 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (2分の1納付の場合)128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (4分の3納付の場合)168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| (3)納付猶予申請 |
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。 <所得額の基準> (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| (4)学生納付特例申請 |
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。 <所得額の基準> 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
※離職者、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
※上記(1)~(4)以外でも障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。(法定免除を受ける際にも申請が必要となります。)
2.産前産後期間の免除制度
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
また、産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、対象となる場合には、役場窓口・電子申請等により、届出をお願いします。
なお、出産後も届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
詳細は、日本年金機構HP(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)をご覧ください。
3.保険料の免除等期間の取扱い(受給資格期間への算入と年金額への反映)について
| 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間に算入されるか?) |
||
| 受給資格期間に 算入されるか? |
年金額に 反映されるか? |
||
| 納付 |  されます |
 されます |
 されます |
| 全額免除 |  されます |
 されます |
 されます |
| 一部納付 (※1) |
 されます |
 されます |
 されます |
| 納付猶予 学生納付特例 |
 されます |
 されません |
 されます |
| 未納 |  されません |
 されません |
 されません |
年金の給付について
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
詳細は、日本年金機構HP(老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額)をご覧ください。
【障害基礎年金】
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間、支給されます。
申請のご相談は役場窓口で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
詳細は、日本年金機構HP(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)をご覧ください。
国民年金基金について
【国民年金基金とは】
国民年金基金は、自営業など国民年金第1号被保険者が、ゆとりある老後を過ごすことができるように、基礎年金の上乗せ給付を行なう年金制度です。
ただし、以下の方は加入できません。
・国民年金の保険料を免除されている方、
・農業者年金に加入されている方、
・国民年金の付加保険料を納めている方
※税金の控除の対象になります。
基金の保険料は、国民年金保険料と同様に社会保険料控除として全額控除されます。
※詳しくは、国民年金基金連合会のホームページをご覧ください。
- 国民年金基金連合会ホームページ
 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 住民課 国民健康保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8209)