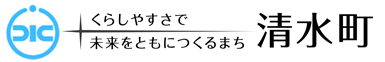幼児教育・保育の無償化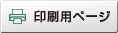
幼児教育・保育の無償化について
令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
無償化の対象者・対象範囲について
・3歳から5歳のすべての子ども(4月1日時点の年齢)
・0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)
・満3歳で幼稚園や認定こども園(幼稚園部)へ入園した場合の利用料は無償化の対象。
※ただし、満3歳後の4月1日を迎えるまでの預かり保育料は非課税世帯のみ無償化対象。
幼児教育・保育無償化イメージ
・0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)
・満3歳で幼稚園や認定こども園(幼稚園部)へ入園した場合の利用料は無償化の対象。
※ただし、満3歳後の4月1日を迎えるまでの預かり保育料は非課税世帯のみ無償化対象。
幼児教育・保育無償化イメージ
| 認可 保育施設 |
幼稚園(新制度移行済) 認定こども園(幼稚園部) |
幼稚園 (新制度未移行) |
認可外保育施設 | |||
| 利用料 | 預かり保育 | 利用料 | 預かり保育 | |||
| 3歳~5歳児 | ◎ | ◎ | ○※ (上限1.13万円) |
○ (上限2.57万円) |
○※ (上限1.13万円) |
○※ (上限3.7万円) |
| 住民税課税世帯の満3歳児 (年度途中で3歳となった子ども) |
― | ◎ | × | ○ (上限2.57万円) |
× | ― |
| 住民税非課税世帯の満3歳児 (年度途中で3歳となった子ども) |
― | ◎ | ○※ (上限1.63万円) |
○ (上限2.57万円) |
○※ (上限1.63万円) |
― |
| 住民税非課税世帯の0~2歳児 | ◎ | ― | ― | ― | ― | ○※ (上限4.2万円) |
◎→全額無償 〇→月額上限あり ×→無償化対象外 ※→「保育の必要性の認定」を受ける必要あり
注意点
・「保育の必要性の認定」については、ご利用の施設経由で認定申請書(施設等利用給付認定)を提出していただく必要があります。また、要件については、65歳未満の同居の親族が就労、傷病・疾病、看護・介護等の事由で自宅での保育が困難である場合に町が保育の必要性の認定を行います。
・預かり保育の利用料は実際にかかった金額と日額単価450円×利用日数、無償化上限額を比べ、低い方が無償化対象額となります。
・認可外保育施設、新制度未移行園を利用している児童は無償化の対象となるために「認定申請書」の提出が必要です。(詳しくは御利用の施設か役場に御確認ください。)
・企業主導型保育施設を御利用の方は、「標準的な利用料」を上限に無償となります。
※令和元年10月以降の標準的な利用料の金額(予定)
・保護者が実費で支払う費用(通園送迎バス代、給食費、行事費等)については、保育料に含まれないため無償化の対象外となります。(特に3歳児から5歳児の副食費については、無償化の対象外となるため、実費での支払いが生じますので、ご注意ください。)
注意点
・「保育の必要性の認定」については、ご利用の施設経由で認定申請書(施設等利用給付認定)を提出していただく必要があります。また、要件については、65歳未満の同居の親族が就労、傷病・疾病、看護・介護等の事由で自宅での保育が困難である場合に町が保育の必要性の認定を行います。
・預かり保育の利用料は実際にかかった金額と日額単価450円×利用日数、無償化上限額を比べ、低い方が無償化対象額となります。
・認可外保育施設、新制度未移行園を利用している児童は無償化の対象となるために「認定申請書」の提出が必要です。(詳しくは御利用の施設か役場に御確認ください。)
・企業主導型保育施設を御利用の方は、「標準的な利用料」を上限に無償となります。
※令和元年10月以降の標準的な利用料の金額(予定)
| 4歳以上児 | 3歳児 | 1、2歳児 | 0歳児 |
| 23,100円 | 26,600円 | 37,000円 | 37,100円 |
保育の必要性の認定について
幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の利用給付を受けるためには、「保育の必要性の認定」が必要となります。この「保育の必要性の認定」につきましては、以下の要件に、保護者及び65歳未満の同居の家族全員が該当し、これを証明する書類を添付して施設等利用給付認定(2号又は3号)の申請をする必要があります。
〇保育の必要性の認定要件と必要書類
〇保育の必要性の認定要件と必要書類
| 事由 | 内容 | 必要書類 |
| 就労 | 家庭外(内)で月64時間以上の就労をしていること | 勤務(内定)証明書(自宅(内)外就労・自営・内職全て) |
| 妊娠・出産 | 母親の出産(予定)日の前後3ヶ月以内 | 母子手帳の表紙と出産(予定)日の記入されたページの写し |
| 疾病・障がい | 保護者が疾病・負傷または心身に障がいがある | 病状内容証明書(町書式)・障がい者手帳の写し |
| 看護・介護 | 同居している家族または親族を常時介護・看護している | 医師の診断書・障がい者手帳の写し・介護保険認定証の写し |
| 災害復旧 | 地震・火災などの災害の復旧にあたっている | 罹災証明書 |
| 求職活動中 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている | 求職活動を証する書類又は当町の求職活動状況報告書 |
| 就学 | 保護者が就学中・職業訓練を受けている | 在学証明書(入学証明書)・カリキュラム等の写し |
- 就労証明書
 (Excelファイル、80KB)
(Excelファイル、80KB) - 病状内容証明書(町書式)
 (PDFファイル、76KB)
(PDFファイル、76KB) - 求職活動状況報告書
 (PDFファイル、105KB)
(PDFファイル、105KB)
申請手続きについて
・幼稚園(新制度移行済)、認可保育所、認定こども園(保育園部)をご利用の方
→申請は必要ありません。
・認定こども園(幼稚園部)をご利用の方
1 預かり保育の利用なし
→申請は必要ありません。
2 共働き等の事由により預かり保育を常時ご利用されている方
→子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の提出と保育の必要性の認定が
必要です。
・幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方
→子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)の提出が必要です。
※共働き等の事由により預かり保育を常時ご利用されている方は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の提出と保育の必要性の認定が必要です。
・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等をご利用の方
→子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の提出と保育の必要性の認定が必要です。
・企業主導型保育施設をご利用の方
→ご利用の施設にお問い合わせください。
→申請は必要ありません。
・認定こども園(幼稚園部)をご利用の方
1 預かり保育の利用なし
→申請は必要ありません。
2 共働き等の事由により預かり保育を常時ご利用されている方
→子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の提出と保育の必要性の認定が
必要です。
・幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方
→子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)の提出が必要です。
※共働き等の事由により預かり保育を常時ご利用されている方は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の提出と保育の必要性の認定が必要です。
・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等をご利用の方
→子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の提出と保育の必要性の認定が必要です。
・企業主導型保育施設をご利用の方
→ご利用の施設にお問い合わせください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
 (PDFファイル、287KB)
(PDFファイル、287KB) - 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
 (PDFファイル、384KB)
(PDFファイル、384KB)
給食費の取扱いについて
給食費については、これまで保育料の一部として保護者の皆様にご負担いただいておりましたが、無償化開始後につきましてもこの考え方を基本とし、次のとおりの取り扱いといたします。
・1号認定(幼稚園利用者)、2号認定(保育所利用の3歳児から5歳児)をご利用の方は、施設に直接お支払いをしていただきます。
・3号認定(保育所利用の0歳児から2歳児)は現行の取り扱いを継続いたします。
・年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の利用者※は副食費が免除となります。(1号・2号のみ)
※第3子以降の利用者とは1号認定(幼稚園利用者)は小学3年生以下の児童、2号認定(保育所利用の3歳児から5歳児)は小学校就学前の児童といたします。
・1号認定(幼稚園利用者)、2号認定(保育所利用の3歳児から5歳児)をご利用の方は、施設に直接お支払いをしていただきます。
・3号認定(保育所利用の0歳児から2歳児)は現行の取り扱いを継続いたします。
・年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の利用者※は副食費が免除となります。(1号・2号のみ)
※第3子以降の利用者とは1号認定(幼稚園利用者)は小学3年生以下の児童、2号認定(保育所利用の3歳児から5歳児)は小学校就学前の児童といたします。
給付方法
給付につきましては町内施設は原則代理受領方式となりますが、町外施設は施設により異なりますので、どちらの方式によるかは施設にご確認ください。
・代理受領払い方式
→利用料か子育てのための施設等利用給付の上限金額の内、低い金額を町から施設に支払います。上限金額を超えて利用した分については、施設から請求されるので、施設にお支払い下さい。
・償還払い方式
→利用者様から利用料を全額施設に支払ったのちに、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して町に請求し、町から指定口座に振り込みます。
・代理受領払い方式
→利用料か子育てのための施設等利用給付の上限金額の内、低い金額を町から施設に支払います。上限金額を超えて利用した分については、施設から請求されるので、施設にお支払い下さい。
・償還払い方式
→利用者様から利用料を全額施設に支払ったのちに、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して町に請求し、町から指定口座に振り込みます。
参考
幼児教育・保育の無償化についてはこちら(外部ページ)
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 児童育成係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8227)