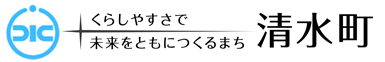2025年9月30日 更新
住宅セーフティーネット制度について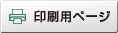
住宅セーフティーネット法とは?
住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)は、 低額所得者や高齢者など、住宅の確保が困難な方々(住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」という))が 安心して賃貸住宅に入居できることを目的として制定された法律です。
令和7年10月1日から住宅セーフティネット法の一部が改正されます。
主な改正点は、以下の3つになります。
1. 賃貸市場環境の整備(大家さんの不安解消)
これは、大家さんが住宅確保要配慮者に住宅を貸しやすくするための措置です。
・終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化
これまでは住宅ごとに認可が必要だった「終身建物賃貸借」(入居者が亡くなると契約が終了し、相続人に引き継がれない契約)が、事業者単位での認可に変更されます。これにより、大家さんの手続き負担が大幅に軽減されます。
・残置物処理に関する規定の追加
入居者が亡くなった際の残置物処理を、居住支援法人の業務として明確化しました。これにより、大家さんが孤独死などを懸念して賃貸をためらう大きな要因を減らすことを目指しています。
・家賃債務保証業者の認定制度の創設
住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を、国土交通大臣が認定する制度が創設されます。これにより、家賃保証が受けやすくなり、大家さんの家賃未払いの不安を軽減します。
2. 「居住サポート住宅」の供給促進
・「居住サポート住宅」認定制度の創設
見守りや安否確認、福祉サービスへのつなぎといった生活支援サービスを併せて提供する住宅を「居住サポート住宅」として認定する制度が始まります。これにより、単なる住居提供にとどまらない、より包括的な支援が可能になります。
・生活保護受給者の家賃代理納付の原則化
居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合、家賃を福祉事務所が大家さんへ直接支払う「代理納付」が原則化されます。これにより、家賃の未払いのリスクが軽減され、大家さんが生活保護受給者へ積極的に住宅を提供しやすくなります。
3. 地域における居住支援体制の強化
・居住支援協議会の設置促進
住宅と福祉の連携を強化するため、市区町村による居住支援協議会の設置が努力義務化されます。これにより、行政や民間団体が連携し、地域の住宅確保要配慮者の支援を一体的に進められるようになります。
1. 賃貸市場環境の整備(大家さんの不安解消)
これは、大家さんが住宅確保要配慮者に住宅を貸しやすくするための措置です。
・終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化
これまでは住宅ごとに認可が必要だった「終身建物賃貸借」(入居者が亡くなると契約が終了し、相続人に引き継がれない契約)が、事業者単位での認可に変更されます。これにより、大家さんの手続き負担が大幅に軽減されます。
・残置物処理に関する規定の追加
入居者が亡くなった際の残置物処理を、居住支援法人の業務として明確化しました。これにより、大家さんが孤独死などを懸念して賃貸をためらう大きな要因を減らすことを目指しています。
・家賃債務保証業者の認定制度の創設
住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を、国土交通大臣が認定する制度が創設されます。これにより、家賃保証が受けやすくなり、大家さんの家賃未払いの不安を軽減します。
2. 「居住サポート住宅」の供給促進
・「居住サポート住宅」認定制度の創設
見守りや安否確認、福祉サービスへのつなぎといった生活支援サービスを併せて提供する住宅を「居住サポート住宅」として認定する制度が始まります。これにより、単なる住居提供にとどまらない、より包括的な支援が可能になります。
・生活保護受給者の家賃代理納付の原則化
居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合、家賃を福祉事務所が大家さんへ直接支払う「代理納付」が原則化されます。これにより、家賃の未払いのリスクが軽減され、大家さんが生活保護受給者へ積極的に住宅を提供しやすくなります。
3. 地域における居住支援体制の強化
・居住支援協議会の設置促進
住宅と福祉の連携を強化するため、市区町村による居住支援協議会の設置が努力義務化されます。これにより、行政や民間団体が連携し、地域の住宅確保要配慮者の支援を一体的に進められるようになります。
居住支援法人とは
居住支援法人は、地域で居住支援の活動に取り組む法人として、住宅セーフティネット法に基づき都道府県が指定する法人です。
指定を受けるには、各都道府県へ申請が必要となります。
指定を受けるには、各都道府県へ申請が必要となります。
- 詳細はこちら(静岡県ホームページ)
 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます)
- 静岡県居住支援法人の紹介
 (PDFファイル、114KB)
(PDFファイル、114KB) - 静岡県居住支援法人の一覧
 (PDFファイル、583KB)
(PDFファイル、583KB)
大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック
国土交通省は、住宅セーフティネット制度の活用が促進されるよう、住宅確保要配慮者の受け入れにあたり、大家さんからよくいただくご質問とその答えをまとめた「大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」を作成しました。
また、大家さんからの相談を受ける仲介業や賃貸管理業などの不動産関係団体をはじめとする関係者の方々に制度へのご理解を深めていただくために、ハンドブックの解説や住宅セーフティネット制度の概要、お役立ち情報を掲載した解説版も合わせて作成しています。
また、大家さんからの相談を受ける仲介業や賃貸管理業などの不動産関係団体をはじめとする関係者の方々に制度へのご理解を深めていただくために、ハンドブックの解説や住宅セーフティネット制度の概要、お役立ち情報を掲載した解説版も合わせて作成しています。
- 詳細はこちら(国土交通省ホームページ)
 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます)
- 「大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」
 (PDFファイル、633KB)
(PDFファイル、633KB) - 「大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック 解説版」
 (PDFファイル、5.6MB)
(PDFファイル、5.6MB)
セーフティーネット住宅とは
セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、県、政令市の登録を受けた住宅をいいます。
登録された住宅は入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこととなっております。
静岡県では、登録されたセーフティネット住宅の情報を、住宅確保要配慮者等に情報提供しています。
町内のセーフティネット住宅は、静岡県への登録が必要となります。
静岡県住まいづくり課(電話:054-221-3081)
登録された住宅は入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこととなっております。
静岡県では、登録されたセーフティネット住宅の情報を、住宅確保要配慮者等に情報提供しています。
町内のセーフティネット住宅は、静岡県への登録が必要となります。
静岡県住まいづくり課(電話:054-221-3081)
- 詳細はこちら(静岡県ホームページ)
 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます)
生活困窮者自立支援相談
社会福祉協議会では、経済的に生活が困窮し、生活に困りごとや不安のある方の相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
清水町社会福祉協議会 清水町堂庭221番地の1
清水町福祉センター内 電話:055-981-1675
清水町社会福祉協議会 清水町堂庭221番地の1
清水町福祉センター内 電話:055-981-1675
- 生活困窮者自立支援相談について(清水町社会福祉協議会ホームページ)
 (別ウィンドウで開きます)
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)