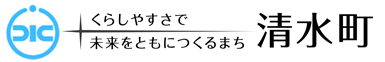2025年4月1日 更新
児童扶養手当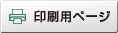
児童扶養手当は、ひとり親世帯で児童を養育している家庭の生活の安定と、自立促進に寄与するために支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。
※公的年金を受けていても、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額が受給できます。
平成26年12月から、年金を受給していても児童扶養手当額を下回っている場合は、差額を受け取れるようになりました。
※令和3年3月1日から児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わりました。
児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
※公的年金を受けていても、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額が受給できます。
平成26年12月から、年金を受給していても児童扶養手当額を下回っている場合は、差額を受け取れるようになりました。
※令和3年3月1日から児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わりました。
児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
- 厚生労働省お知らせ(公的年金等)
 (PDFファイル、418KB)
(PDFファイル、418KB) - 厚生労働省お知らせ(障害年金等)
 (PDFファイル、525KB)
(PDFファイル、525KB)
請求者(受給者)
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害がある児童)を監護し、生計を同じくする母(父)または母(父)に代わって児童を養育している人。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童
所得の制限
請求者や同居者の所得に応じて支給額に制限があります。前年の所得額や税法上の扶養親族の数に応じて制限額が異なります。
※請求者の所得が制限以内であっても、同居の扶養義務者の所得が制限額以上の場合は、手当は支給されません。
※令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部改正により、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
以下、扶養親族の数が1人増えるごとに、所得制限限度額に380,000円を加算します。
※請求者の所得が制限以内であっても、同居の扶養義務者の所得が制限額以上の場合は、手当は支給されません。
※令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部改正により、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
| 扶養親族の数 | 手当の全額支給 | 手当の一部支給 | 同居の扶養義務者 |
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
以下、扶養親族の数が1人増えるごとに、所得制限限度額に380,000円を加算します。
支給金額(月額)
令和7年4月分からの支給月額は下記のとおりです。
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人 | 46,690円 | 46,680円~11,010円(所得に応じて決定) |
| 2人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円~5,520円(所得に応じて決定) |
手当の認定申請について
児童扶養手当の支給を希望する方は、「児童扶養手当認定請求書」を記入のうえ、必要書類を添付してこども未来課に提出してください。
必要書類
・戸籍謄本(請求者と対象児童が載っているもの、離婚の場合は離婚の記載があるもの)
児童が入籍していない時は児童の戸籍謄本も必要です。
・年金手帳(基礎年金番号が確認できるもの)
・請求者名義の預金通帳等の写し
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(請求者本人・対象児童分)
また、世帯の状況により、配偶者・扶養義務者の分の個人番号を記載する必要があります。
※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、事前にこども未来課窓口に御相談にお越しください。
児童が入籍していない時は児童の戸籍謄本も必要です。
・年金手帳(基礎年金番号が確認できるもの)
・請求者名義の預金通帳等の写し
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(請求者本人・対象児童分)
また、世帯の状況により、配偶者・扶養義務者の分の個人番号を記載する必要があります。
※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、事前にこども未来課窓口に御相談にお越しください。
手当の支給開始月
認定請求手続きをした翌月分から支給対象となります。
手当の支給月
年6回奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に支払月の前2か月分が支給されます。
支払日 各支払月の11日(土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。)
支払日 各支払月の11日(土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。)
現況届
毎年8月に受給者及び同居の扶養義務者の前年の所得や支給要件の確認のため、現況届の提出が必要です。
受給者の方には、事前に現況届の提出のお知らせを郵送しますので、提出期限までに必ず提出してください。
※提出期限を過ぎると、次回の手当の支給が停止する場合があります。
※2年間現況届の提出がない場合、受給資格がなくなる場合があります。
受給者の方には、事前に現況届の提出のお知らせを郵送しますので、提出期限までに必ず提出してください。
※提出期限を過ぎると、次回の手当の支給が停止する場合があります。
※2年間現況届の提出がない場合、受給資格がなくなる場合があります。
その他の届出
次の場合は届出が必要です。届出が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合や、支給した手当を返納していただく場合があります。
・手当を受ける資格がなくなったとき
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・金融機関を変更するとき
・支給対象児童が増加(減少)したとき
・世帯の構成が変わったとき
・公的年金等の受給したとき(受給できるようになったとき)
・手当を受ける資格がなくなったとき
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・金融機関を変更するとき
・支給対象児童が増加(減少)したとき
・世帯の構成が変わったとき
・公的年金等の受給したとき(受給できるようになったとき)
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)