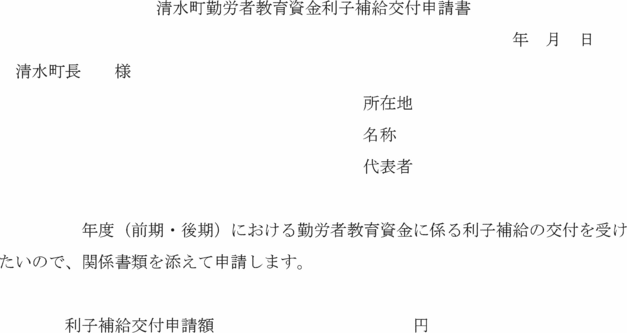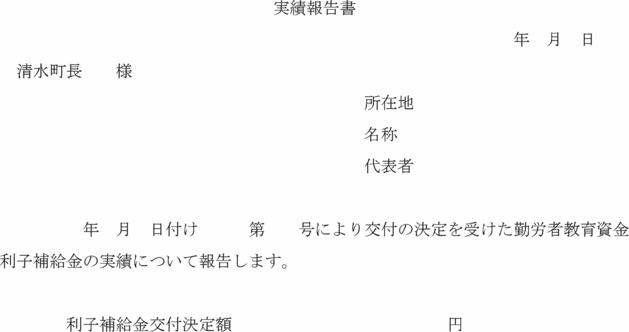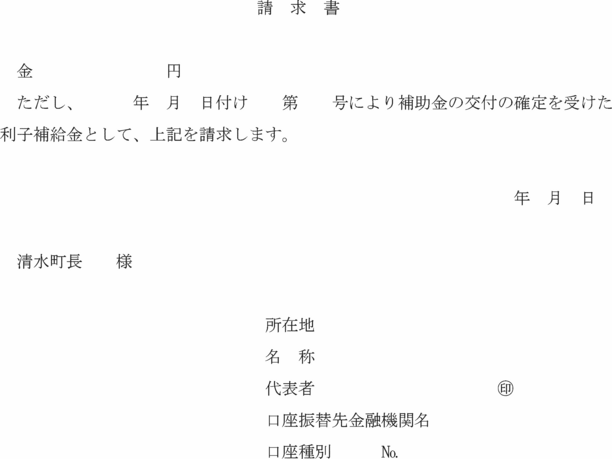第1条 町長は、勤労者の教育に係る経済的負担の軽減を図るため、勤労者に教育資金を貸し付ける静岡県労働金庫(以下「労働金庫」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、
清水町補助金等交付規則(昭和62年規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 大学等
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校のうち、次に掲げるものをいう。
イ 専修学校の専門課程(修学年限が2年以上のもの)
エ 専修学校の高等課程(修学年限が3年以上のもの)
(3) 教育資金 勤労者又はその2親等以内の親族が大学等の入学時又は在学中に要する資金をいう。
第3条 利子補給の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町に記録されている者で引き続き1年以上本町に居住している勤労者
(2) 勤労者又はその2親等以内の親族が大学等の入学試験(推薦入学を含む。)に合格した者又は大学等に在学している者
(3) 勤労者の前年の収入が1,000万円未満であって、この要綱のよる貸付けを受けなければ、勤労者又はその2親等以内の親族が大学等への進学又は在学が困難な者
第4条 労働金庫から借り受けた教育資金のうち利子補給の対象となる額は、1人につき300万円を限度とする。
第5条 利子補給の期間は、第1回の償還日から5年とする。ただし、当該期間内であっても、労働金庫から借り受けた教育資金に係る大学等へ進学しないとき、勤労者若しくはその2親等以内の親族が当該期間内に大学等を退学したとき、又は第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったときは、以後の利子補給を打ち切るものとする。
第6条 利子補給の額は、勤労者が第4条に規定する限度内の教育資金を次に掲げる条件により借り受けたものを対象とし、当該教育資金の残高を年利1.7パーセントにて借り受けたものとして算出した利子の額のうち、毎年4月1日から9月30日まで(以下「前期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「後期」という。)の各期間における支払うべき利子の額に相当する額とする。ただし、勤労者が労働金庫から借り受けた教育資金の年利率を超えないものとする。
(1) 償還期間 10年以内(元金償還据置期間最長4年6月を含む。)
(2) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦・半年割賦償還の併用
第7条 労働金庫は、利子補給金の交付を受けようとするときは、前期分にあっては10月5日までに、後期分にあっては翌年度の4月5日までに、清水町勤労者教育資金利子補給交付申請書(
様式第1号)に利子補給金の計算基礎等を明らかにする書類(以下「計算内訳書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定通知書により労働金庫に通知するものとする。
第8条 前条第2項の規定による通知を受けた労働金庫は、第6条に規定する期間に係る利子補給金について、それぞれの期間終了後、前期分にあっては10月10日までに、後期分にあっては翌年度の4月10日までに、実績報告書(
様式第2号)に計算内訳書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付確定通知書により労働金庫に通知するものとする。
第9条 労働金庫は、前条第2項の交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内に請求書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(清水町勤労者生活資金及び教育資金貸付制度要綱の廃止)
2 清水町勤労者生活資金及び教育資金貸付制度要綱(昭和56年要綱第19号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の清水町勤労者生活資金及び教育資金貸付制度要綱の規定により貸し付けられている勤労者生活資金及教育資金については、なお従前の例による。

様式第1号
(第7条関係)
様式第2号
(第8条関係)
様式第3号
(第9条関係)